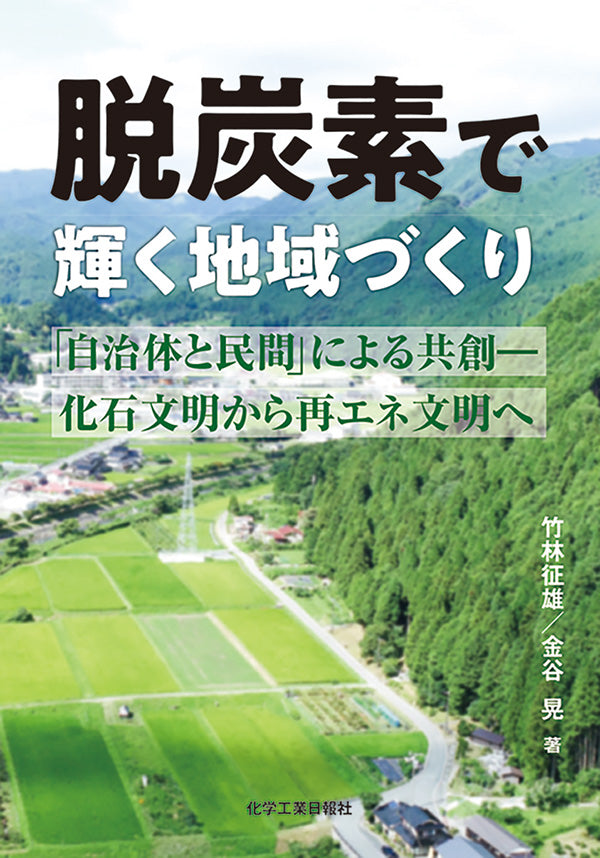化学工業日報
脱炭素で輝く地域づくり
受取状況を読み込めませんでした
沸騰する地球、温暖化対応は手遅れか?
今こそ自治体と市民協働による脱炭素⇒価値向上+活性化!
■脱炭素で輝く地域づくり
「自治体と民間」による共創-化石文明から再エネ文明へ
竹林征雄/金谷 晃 著
◎A5判・284頁
◎定価:3,300円(本体3,000円+税10%)〒別
◎ISBN978-4-87326-770-8 C3033
◎2024年6月18日発売
本書は、あなたが主となり地域とともに脱炭素化社会の形成を進め、同時に衰退する地域を、再生可能エネルギー活用により安心安全、安定した持続的な「暮らしも生業も」成り立つことを目指すものとして執筆されました。
再生可能エネルギーを基軸として、地域力、稼ぐ力をつける脱炭素化社会の形成には、基礎自治体である市町村の現実的、具体的な取り組みが不可欠です。地域の特性に合わせた目指すべき明確な長期ビジョンの作成や、それに向けた脱炭素戦略や事業遂行に関係する方々との連携体制の構築などに取り組む例として、脱炭素先行地域である群馬県上野村を取り上げています。
本書が、家庭や企業や役所内でも「気候変動による温暖化問題」に対する世界と国内の状況、今後の対応を理解し、具体的な対応策と実践に役立ち、あなたと地域に気づきをもたらす書となるでしょう。
【目 次】
推薦のことば/加藤 三郎
推薦のことば/小磯 修二
出版に寄せて-脱炭素がつなぎ脱炭素で輝く地域コミュニティ/群馬県上野村 村長 黒澤 八郎
はじめに-皆で進める脱炭素化とまちづくり
最初に-脱炭素は、日本最大の産業振興
「これまでの気候と社会」
「脱炭素におけるエネルギーの需要と供給」
「温暖化と21世紀」
「脱炭素化はエネルギーと裏表」
第1部 岐路に立つ人類
1.パリ協定(COP21)で世界が一変
1-1.なぜ温暖化に、地球は沸騰の時代に
(1)温室効果による地球
(2)過激な温室効果の主因は、CO2大量排出
(3)氷期(寒冷)と間氷期(温暖)の経年変化
(4)気候極端現象出現
(5)二酸化炭素による温室効果の発見
1-2.温暖化は人類の責任、パリ協定「1.5℃の約束」
(1)IPCCについて
(2)1992年リオデジャネイロ会議、2007年IPCC報告
(3)2015年第21回パリ会議(COP21)、温暖化主犯は人間
(4)2021年第26回グラスゴー会議(COP26)と
2023年インドG20
(5)2023年ドバイ会議(COP28)
1-3.日本のエネルギー事情と再生可能エネルギー
(1)エネルギーの消費と需要推移および基本的視点、
課題ではエネルギーの今後はどうなるのか、
考えてみましょう
(2)エネルギー多消費産業の化学工業界脱炭素対応事例
(3)エネルギーと家庭
(4)エネルギー問題による国民の痛み
(5)再生可能エネルギーへの転換、脱炭素対応
2.脱炭素による新しい社会
2-1.温室効果ガス削減目標 2030年
2-2.新エネルギー政策 日本版GX
(1)GXによる温暖化対策
(2)G7合意と日本の脱炭素
(3)GX課題
2-3.脱炭素は地域再生とグリーン経済の要
(1)無限の経済成長はあり得ない
(2)シュタットベルケ
(3)事業の主体は、エネルギーに軸足
(4)ベネフィット・コーポレーション
(5)脱炭素と経済循環…地域内乗数
2-4.脱炭素とSDGs、ESG投資との相関
(1)SDGsの構成
(2)脱炭素エネルギーSDG7と8項目のSDG
(3)まちづくりSDG11と16項目のSDG
(4)ESG投資とSDGs
3.脱炭素への支援体制、メニュー概要
3-1.脱炭素社会への地域転換は?
(1)推進課題
(2)市町村の業務
(3)温暖化対策の推進方策
3-2.国の脱炭素支援
第2部 ビジョン編
4.将来像としてのビジョンづくり
4-1.脱炭素ビジョンは、地方創生の視座が重要
4-2.地域課題の抽出
(1)総合計画の施策を確認
(2)地方創生の視座から地域課題を抽出
4-3.地域課題の解決策に資する脱炭素対策を選定
4-4.ビジョン達成による効果を考える
4-5.伝えるためのビジョンの仕上げ
第3部 計画編
5.実効性ある計画づくり
5-1.脱炭素計画をつくる際に知っておきたい基礎知識
(1)対象とすべき温室効果ガスと部門の範囲
(2)電気は使用量が増えてもCO2は減ることがある
(3)CO2排出量の按分推計は実態とかけ離れることがある
(4)再エネのポテンシャル量と本当に利用できる量は
異なる
(5)地域脱炭素事業の促進には官民連携が必須
5-2.計画づくりの体制検討
5-3.現状を知る(温室効果ガス、再エネ・省エネへの
取組)
(1)温室効果ガスの排出量
(2)再エネの導入・稼働状況
(3)省エネ等の取組状況
5-4.再エネの現実的な利用可能量を知る
5-5.再エネ導入と省エネ対策の施策を検討する
5-6.目標を設定しロードマップを作成する
5-7.地域の課題解決による社会・経済効果を整理する
5-8.関係者との連携体制と合意形成の基盤をつくる
5-9.計画推進に係る庁内体制を検討する
5-10.地域脱炭素化を促進する区域を設定する
6.国の支援施策を活用した計画づくり
資料編/用語集
【座談会】脱炭素先行地域の取り組み-群馬県上野村
おわりに